仮庵の祭り 《仮庵の祭りでは、イスラエルの民は小さな小屋に籠もり、神からの救いに預かった歴史を顧みながら神に祈りを捧げましたが、琉球でも昔は祭りの日になると、藁で作られた小さな小屋で月を眺める風習が一部の島で続いていました》 (筆者注:《藁で作られた小さな小屋で月を眺める》祭は、自然信仰である月への信仰であってイスラエルの神ではないと考えられます)
アダムとイブ(エヴァ) 《聖書には人類の祖先としてアダムとイブの話が記載されています。同様に沖縄の離島、古宇利島でも裸の男女の子供が餅を食べて生活をし、その子孫から沖縄の人々が誕生したという言い伝えが残されています。また、沖縄には男はソーキブニ、肋骨が1本足りない、という言い伝えがあります。それは女性の為に男が愚になることを言い表していますが、イスラエルの民も聖書の記述から、女性は男性のあばら骨の一つから作られたと信じていました》
ニライカナイ 《沖縄古来の「ニライカナイ」信仰によれば、遥か遠い東の海の彼方に楽園があり、そこから沖縄の神はやってきたと信じられていたことにも注目です。イスラエルの民も、東の島々に約束の地があることを信じて琉球界隈まで到来しましたが、そこは単なる玄関に過ぎず、その先に更に目的地に繋がる島々があるという認識を持っていたのです。つまり、「ニライカナイ」信仰と同様に琉球諸島の先には、永遠の命に至る理想郷、約束の場所があるとイスラエルの民も信じていたのです》 《「ニライ」はneer、ニー(neer、ニー)とi、イ(i、イ)という2つのヘブライ語を混合した言葉です。前者はイスラエルのキブツと呼ばれる集団生活の拠点を称する名前の頭3文字としても頻繁に使われる言葉です。原語の意味は「耕された畑」です。つまり、「ニー」、「ニラ」とは、穀物が収穫できる良地を象徴する言葉であり、それ故、イスラエルのキブツの名称に用いられています。また、後者の「イ」は島を意味します。すると「ニライ」とは、「耕された畑の島」、すなわち、食物が豊かで、居住しやすい楽園の島を意味することになります》 《「カナイ」の語源を理解するために、ヘブライ語で「取得」を意味するkanah、カナ(kanah、カナ)の語尾が変化したkanooy、カヌイ(kanooy、カヌイ)という言葉に注目してみました。この言葉には土地や名声を手にするという意味があり、取得して後、その土地に永住するというニュアンスが含まれています。すると、「ニライカナイ」の意味がヘブライ語で明確になり、直訳すると「耕された畑の島を得て長く住む」という意味を持つ言葉であったことがわかります。すなわち「ニライカナイ」とは、食物に溢れ、長寿を全うできる「理想郷の島」で永住することを意味していたのです。それは正に、神がイザヤに約束した東の島々を意味するものであり、イザヤの一行が目指した最終の目的地を指していたのです》 (前掲ウェブサイト『日本とユダヤのハーモニー&古代史の研究』)
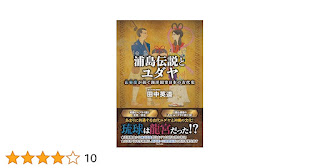



0 件のコメント:
コメントを投稿