https://yatsu-genjin.jp/suwataisya/sinji/suwaumi2.htm
菅江真澄が見聞した「御頭祭」を読み解く '10.1.10
写本『すわの海(秀雄北越記本)』を底本としました。時代が違うので直に当てはめることはできませんが、『諏方大明神画詞』や『年内神事次第旧記』の「酉の祭(御頭祭)」を参考に、菅江真澄が見聞したものを無理のないように書き換えてみました。

前官の十間廊に、鹿の頭が75もマナ板の上に並んでいた。その中に耳が裂けた鹿があるが、それは神の矛で切られたものだと言う。権祝・神正庸(かんまさつね)の和歌がある。
「かねてしも神の御供え耳さけの鹿こそ今日の贅となるらめ」
このように集まった鹿は、余ることはあっても足りなくなることはないそうだ。
▼「上社七不思議」の一つ「高野の耳裂鹿」。雄同士の縄張り争いの中で耳がツノで裂かれたもので、特に珍しいというものではない。▼「必ず75頭以上集まる」と言われているが、実情は猪を含めた数。それも塩漬けやミイラ化した物も含むと言うから…。足りない場合は、魚などの「決められた代用品」を用意する。(75も並べたら人が座る場所がなくなる。冷蔵庫がないから臭いが…)
裃(かみしも)を着た男が二人、何かの肉をマナ板に載せて出てきた。足さばきなどから、定まった形があるように見える。
廊内には弓矢・鎧(よろい)が飾ってある。剣は「根曲太刀」と言って、柄の下が曲がっている。世に二つと無い宝だ。
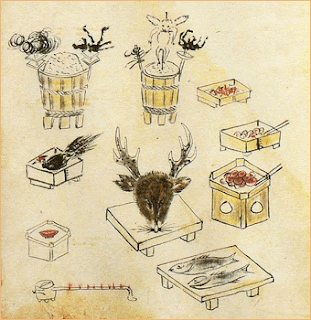
大小の魚・毛が固いものや柔らかい獣などを全て揃え、色々な形をした台に載せて神前に置かれている。大祝は都合で欠席したので、代わりに、箱に入った(大祝が着る)山バト色の御装束が敷皮の上に置かれていた。
酒肴が調った。神長より下座の敷皮に座っている神官が盃を取ると、提子(ひさげ)を持って注ぎ廻っている。肴は何回もお代わりをし、小さな折(オリ)にモチ・カヤ・ヤマイモなどを取って入れている。
しばらくすると神長官が敷皮から立ち上がり、ある柱のもとに行った。弓矢を持っているが、射ったのだろうか。多くの人が群がっていて見えなかった。ヨシ(葦)で作ったムシロを敷き、その端に沿って神長官と他の神官が並んだ。
▼『上宮神事次第大概』に「頭郷から選ばれた両人が潔斎の後、麻の裃を着けて、雁と包丁と箸とを載せたマナ板(95×35×14cm)を大祝に供える」とある。「包丁式」があったと思われる。▼「根曲太刀」は宝剣なので腰に挿すことはない。今回は大祝が欠席したが、本来はその横に太刀持ちの宮島氏が捧持して控える。▼ 弓矢は「蟇目鳴弦」用で、祭場の邪気払いをしたと思われる。神事の順番からは、『神長神事次第書状』の「八鉾の矢西門に参り御腰物参る」が当てはまる。▼「はなをそえて」とあるが、前後の文脈から「はな」を「花ではなく端」にした。
(訊くと)御杖を御賛柱と言う人がいるが、これはそうではないと言う。およそ長さ五尺・巾五寸の尖っている柱を押し立てた。神長官が御座より下りて柱を調べると、「これは節があって良くない」と言った。
▼ 御杖柱の規格が「節のない桧」とわかっているのに、なぜ節付きの柱を用意したのかわからない。▼「よからじ」を"方言"の「肯定」とすれば、「節はあるがよかろう」となり、次の「取りあえず(直ちに)」に繋がる。長さ2.5mと書かれた記録があるから、「節なし」の手配は難しかったと思われる。
御神(おこう)と言う八歳くらいの子供に紅色の装束を着せた。人々は、そのおん柱に子供の手を添えさせたまま運んで高ムシロの上に置いた。
木綿襷(ゆうタスキ)をかけ山吹色の服を着た者が待機している。裃を着た男が小さな錦の袋から「藤刀」を出し、抜き放ったものを神長官に渡した。神長官は、藤刀を柱の上にいったん置いてから山吹色の着物を着た神官に渡した。その後に長い縄を取って渡した。
▼ 柱が杖だった中世では、神使が「御杖」を捧持して大祝に渡したとある。その名残が(柱では重くて持てないから)「手を添えて」になるのだろう。その後、当然ながら神使は座に戻る。▼「たかむしろ」は一般には竹筵だが、「彼(か)の」は前述の「よしの束縄」のことだから、高座に敷いた「葦のムシロ」となる。
木綿襷を掛けた神官が、藤刀で頂部から刀(の長さ)に等しい場所に刻みをつけて、サワラの枝・ヤナギの枝・きさ(ジシャ)の小枝を縄の端で結(縛)った。
矢を一本結ってから三の枝を結う。反対側も矢一本を結う。さらに、刀に等しい位置に刻み目を付けて、(上下)二箇所を結ぶ。(やり方は)前に同じ。左右に向けて結い分けると縄が残るので、藤刀に合わせて切り放した。
▼ 刻みを付けるのは、縄がズレないようにするため。▼ 原文は「かのはな」で、「彼の」は「長き縄」を指している。▼「刀に等しく・合わせて」から、藤刀を物差し代わりに使ったことがわかる。これによって、縛る位置と結んで余った縄の長さが同じとなる(絵図参照)。▼菅江真澄のスケッチにあるように、「上と下の二ヶ所を縛った縄は、左右反対側に向けて結んだ」と解釈できる。矢は、矢尻を削いだ状態で描かれている。言うまでもないが、藤刀はあくまで御杖柱の細工用。
また、柏葉の周囲を折り曲げて折箸で縫い通したものに糀を盛り、柏の葉で蓋をした(柏酒)。それを四つ御杖柱にさして、十間廊の中央に立てた。
▼ 枯葉では折れやすいので、去年の内に塩漬けにでもしてあったのだろう。菅江真澄が書いた「糀」は、玄米に糀を練り合わせて「醸酒」の代わりとしたもの。ここではフタの接着剤も兼ねた。
神官達が祓詞を奏上すると、北にある神子屋から御神楽が聞こえてきた。柏手が三つ聞こえると、神楽が止んだ。大祝が不在なので、代理の神長官が木綿襷(ゆうだすき)を神使の首に掛けた。その時「先ず、先ず」と言った。
▼ 十間廊の西側に、今も神子屋の壇跡が残っている。▼ 原文「桑の木(コウゾ)の皮を縄に縒りていまし(縛)めて、其の縄かけるとき」を、"素直"に「木綿で作った縄を(輪に)縛って、その縄を神使(の首・肩)に掛ける」と読めば、『諏方大明神画詞』の「大祝、玉鬘藤白波を結びて神使の頚に懸く」と一致する。神事に臨んだ場で輪状にしたことがわかる。また、中世では「神使殿にゆう(木綿)かけ申す」、天保年間では「神使は、…藤皮を襷(たすき)として…」と記録にある。▼「まづまづ」に「先ず」を当てたが、意味はわからない。
用意させた燭台の灯りで、祝が箱に入っている祭詞を読み終えると、礼服を着た男(頭主)が神使を背負って、退出した。
▼ 紋付き羽織を着た「世襲の頭主(小坂村の祭礼責任者)」と思われる。▼神使は長期に渡る精進潔斎の後なので、「立っているのがやっと」と言われている。「神子(巫女)などが介添えした」という記述もあるから、当に「フラフラ」だったと思われる。神長守矢史料館の『しおり』では「(縛ったはずの)子供を追いかけて神前へ出てくる」としているが、神事の進行を無視した意訳。「おいて」は"追いて"ではなく"負いて"。▼「まかり出る」は「退出」と理解すべきで、頭首が「背負って出た」となる。また、神使は長い麻布(こうはら※後述)を付けているので、当然ながら一人では歩けない。
神長官が、藤ヅルが茂った木のもとに向かって、「やつくりたりしとき、やねさせるひなのときもの(原文)」を八つ投げた。「やつがり」だろうか。神長官が、高嶋藩主が遣わせた馬の頭に向かって祈念した。
▼ これは難解。『しおり』では「家を造るときに屋根に差した小さな刃物」としているが、私には「何のこと」かさっぱりわからない。▼文末に「御くに司(つかさ)は、諏訪明神の末裔」とあるから、「すはのくにのつかさ」は高嶋(諏訪)藩主となる。使者が乗ってきたのではなく、神使が乗る馬を藩主が用意した。▼「馬への申し立て」は文献にもある。
この馬を速く走らせると、小供たちがその後を追い廻した。
▼ 天保年間の『信濃奇勝録』では「御杖柱を飾立て神使の駈騎(かけのり)あり。藤皮を襷とし、はんひ(半臂)とて腰に二丈五尺(7.5m)の麻布(こうはら)を付神原を乗回す」とある。しかし、菅江真澄は「神使が馬に乗った」とは書いていない。▼ 前中半の詳細な観察に比べ、後半の(誤認とも思える)手抜きの描写は、人垣と神事終盤の混乱で見えなかったとするのが妥当だろう。ここでの「高島藩主から…」以降の描写は、実際には見えなかった(見ていなかった)としたい。そのほうが文脈としては理屈に合う。

▼ 中世では「御杖捧持・神使の付き添い・御宝捧持は村代神主の役」とあるが、この時代では御頭郷の"役員"が担当した。▼「早く走らせた馬」の後を「ゆっくり走った」とあるが、これでは行列にならない。神使が馬を操れるとは思えないから、従者が轡(くつわ)を持って先導する速さとなる。また、2mを越す御杖柱を含む行列だから、やはり「早足」程度で「御手払道」を回ったのだろう。▼「七回」という数に当てはまるものが文献にない。▼「皆帰る」とあるので、これで前宮での神事のすべてが終わったのだろう。「神使廻湛」はすでに廃れていたことがわかる。当然ながら、大祝等の神官は本宮へ戻り"修了式"を行う。▼ それにしても、クライマックスと言うのに肩すかしのような(あっけない)「終わり方」に疑問が残る。
神長官の屋敷に神社があり、その社前で神使の縄を解いて放すそうだ。また、大祝は諏方明神の子孫で、諏訪藩主も同じ。神長官も守屋の大臣の末裔であると言う。
▼「長殿の庭」とあるから、神事終了後は前宮から神長官屋敷に戻り、(今で言う)御頭御社宮司総社の前で御社宮神を昇神させ、玉鬘を外して「お役ご免」となる。『諏訪史第二巻後編』では、明治初年頃の"談"として「神長官邸内に設置せられたる精進小屋に帰る」、幼年の頃の実見として「神願門より乗馬して御手祓道を三匝し畢って何れかへ往った」とある。▼ この段落の終止は「あるなる・となん・とかや」の推測なので、自分で見たのではなく、周りの人から聞いたものや文献にあるものを書き加えたのだろう。
普賢堂の桜を見ながら帰ると、すでに6時(5時から7時)に近かった。上社本宮を拝んで帰った。
「平成の御頭祭」でも人垣でよく見えないから、菅江真澄も、リアルタイムの記録ではなく記憶を元にまとめたのだろう。当然、思い込みや"順不同"があり、聞き取り調査などで補足したと思われる。

以上の釈義は、信濃史料刊行会『新編 信濃史料叢書』に収録されている菅江真澄「すわの海(写本)」から「御頭祭の部分」を私本として現代語訳したものです。
『神長官守矢史料館のしおり』
『しおり』にある「菅江真澄は次のように書き残している」で始まる文は、『菅江真澄信濃の旅』にある「御頭祭の部分」を転載したものです。この書は「中学校創立記念事業」とあるように、諏訪神社の祭祀に詳しくない(と思われる)著者が中学生向けに書き替えた「読み物」です。
ここではまだ「縄でしばりあげる」だけですが、『しおり』になると「立木に縄で縛りつけるのは何故か」「かつてはおこうは殺されたと伝えられている」と(著者の)コメントが加わります。これが、"すべての誤解の元"でしょう。もっとも、『しおり』は「極簡単にまとめられた手引き書」ですから、少し過激な表現にしたのは理解できます。






0 件のコメント:
コメントを投稿