…竹取翁夫婦と、心は天地の差ではあるが、その家を、天女が離れることを説くためには、こうした二様の形の岐れ道を示すのも、理由のあることである。神となるためには、いったんこの世を見罷って転生するか、ただちに神として昇天するかの二つの、どちらかを選ぶわけなのだ。ところが、この天女は、おなじ山陰道ながら歴史事情のすっかり違ったはずの出雲国でも祀られていた。弥努波というのが、この天女の名である。数箇所にこの名の社があり、また真名井社というのも、祀られている。ところが、同じ国大原郡船岡山の説明には、「郡家の東北一里一百歩にあり、阿波枳閉委奈佐比古命曳き来て、居ゑし船、則、山と化る是なり。故、船岡と云ふ」。ここに出た名は、丹後の和奈佐翁と縁なくはないらしい。しかも、その名に冠した「あはきへ」という語は、「阿波来経」という古格を持った語で、「阿波の国からだんだん経過して来た……」という義である。さらに、阿波の国でいうと、その国でも最も古い歴史のある、今の海部郡海部郷海部浦の地であった。おなじく風土記の、播磨風土記に見えている、「伊射報和気命……勅してのりたまはく、此の貝は阿波国和那散にて我食ひし貝なるかもとのりたまひき」とあるのもそれである。そこは和奈佐意富曾神社という古社の鎮座せられるところである。おほそは、おほぢと通じて、およそ、祖父の義になるのだろうから、丹後では和奈佐老夫という人間であったのが、ここでは、神と崇めた歴史が古いのだ、ということが出来よう。
それに、阿波といえば、旧地の旧地、美馬郡の名の起こりなるみぬまというのは、尊い姫神の神名であった。これを摂津国では敏馬、筑前国では三潴、出雲では、弥努波と前に見えた神の名と同じで、音韻に変化があるばかりの、同じ神の御名であった。そうして、みぬまともみるめとも呼んだ阿波の郡名だが、元の起こりは、この郡の蓁原の弥都波之女神社の神から出たものらしい。この神また、国中の山を越えて、東海岸に、宇奈為神社として示現せられたものと見える。先にあげた摂津の敏馬の神でも、処女神と言うた例があるから、同じ処女を言う髫髪と申したこともうなずかれよう。
二 神をはぐくみ申す者
この処女神であり、髫髪神であるところのみぬはの神を守って対岸の山陽に渡り、山陰へ廻って行った信仰宣布の径路を考えれば、出雲で阿波来経和奈佐比古というのは、丹後の和奈佐老夫であり、またここの和奈佐意富曾に当たるらしいことが考えられる。すわなち、瑞々しく若やかな神を斎いて、その信仰を広めて廻国した神人が、その仕えた神のさらに尊く神成り給うたのにつれて、そのみずからもこの世を去って後、神と祀られることになるのは、まず順道の信仰だ。出雲および元の国阿波での神名の伝えも、それ故あったわけなのだ。それとともに、まだ布教者としての古いおもかげをつきとめていった昔語りでは、丹後の物語のように、ただの老夫と老婦として、きわめて心も人間らしい者と伝えたのである。そうしてその物語から、私どもがとりあげることの出来るのは、髫髪の神に奉仕する神人団のあったことを示す点ばかりであって、この神を虐待し奉ったなどいうのは、附加せられた空想に過ぎぬのである。
だから讃岐造麻呂というても、和奈佐老夫というても幼い神をはぐくみ申した、神人の歴史の大部分の隠れていたのを、表へ浮かべ出した古代人の想像である。
かくのごとく、とくに神々の中に幼い神の在すことを考えることは、諸国の旧社に、その例が、ありあまるばかり多かった。幼い神や、姫神のうつぼ船にはいったまま、海岸または大河に沿うた村里に漂い着かれたことが、いかに広く行きわたって説かれたかは、驚くばかりである。 中には、漂着した船の中で、幼君や姫君は、すでになきがらになっておられたのを、神と斎き初めたなどいう伝えもなかなか多いのである。
似よった多くの伝えの中、最も古くて、活発なのは、少彦名神に関する物語であった。大国主神、国を成すための協力者を思うて、海岸に立っておられた時、蘿摩(ががいも)の莢の船に乗り蛾の皮の裘着て渚に着いた神があり、とりあげて掌に載せれば、飛び上がって頰を嚙み、また手の股から漏き出でたとある。かくのごとく目にもとまらぬ小さな神であった。大国主神を助けて、国を成した後、粟島に渡って、粟稈に攀じ上り、粟稈に弾かれて、常世の国へ渡ったとある。尊い神であって、また幼神としての特徴をそなえ給う神であった。
それに、渡られた常世の国は、海の彼方の神の国土であって、すなわち、少彦名神の、元の国土でもあったわけである。常世国から、この国土への旅を、小さな神であった信仰と結びつけると、天から人間へ流離し給う幼神、ということにもなるのである。
数々の類型の物語の中には、そうして、この国土の事終えて、神の国へ、還るはずのことを、伝えによってはただ、この国にたどりついただけで解決のついたことにする考え方もあり、またこの土において、さまざまの人間苦を経験して後、神となられる形にも伝えた。 そういえば、少彦名神のことよりも、記述の順序でいえば、さらに古いこととして、記されていて、神道学者には、少彦名神と、よく一つにして説かれている淡島、それと蛭子命も、やはり二神の御子ながら、御子の中にはいらずとして、流された方々ということになっている。そうして、生まれながらにして海原へ捨てさせられたのだから、幼神の流離の例にはいるのである。しかも、二柱とも、やや後れた世にみな漂着せられたところを伝えている。蛭子命は摂津西宮へ、淡島神は紀伊加太の淡島へということになっている。さらに蛭子命は、男性の神と考えられているようだが、淡島神は、──少彦名神説をとらぬ限りは──姫神だというふうに考え、後世には、婦人の悩む病いに悩まれ、住吉社の片扉に載せて流されたなどと言われている。みな一つの考え方をたどっていて、それに、時代々々の影を濃く落としているのである。
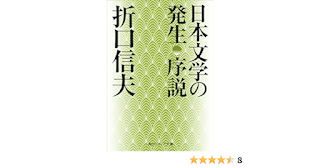



0 件のコメント:
コメントを投稿