日本の鬼の交流博物館
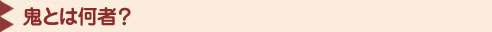


 鎌倉時代に「ヲ二」と書かれた棟端飾瓦が登場し、はっきりと角をもった鬼の顔が刻みこまれ、鬼面瓦としての形が明確になってきます。鎌倉時代までは型造りでしたが、室町時代に入ると手造りにかわり、強さを感じさせる鬼から恐ろしい鬼に変わっていきます。江戸時代に入ると、一般民衆の家にも鬼面瓦が姿をみせますが、近隣の家を睨みつけるので敬遠され、願いごとを記す意味もあって鬼面でない鬼瓦-例えば火災よけのための水のかたち、家内円満の願いをこめた福の神の鬼瓦が飾られるようになってきます。
鎌倉時代に「ヲ二」と書かれた棟端飾瓦が登場し、はっきりと角をもった鬼の顔が刻みこまれ、鬼面瓦としての形が明確になってきます。鎌倉時代までは型造りでしたが、室町時代に入ると手造りにかわり、強さを感じさせる鬼から恐ろしい鬼に変わっていきます。江戸時代に入ると、一般民衆の家にも鬼面瓦が姿をみせますが、近隣の家を睨みつけるので敬遠され、願いごとを記す意味もあって鬼面でない鬼瓦-例えば火災よけのための水のかたち、家内円満の願いをこめた福の神の鬼瓦が飾られるようになってきます。屋根に鬼瓦をのせているのは、世界の中でも日本だけに見られる風景です。どうして鬼瓦が屋根の棟にとりつけられることになったのか不思議なことですが、外部から侵入してくる目に見えない恐ろしい悪鬼、悪霊を退散させる、つまり「魔除け」のためにすえられたものとしか考えようがありません。
邪悪な鬼を退散させるために、いかめしい鬼の顔を彫った瓦を魔除けにすることは奇妙に感じられますが、昔の人々は鬼の中に二面の性格を見いだし、人間に危害を加える好ましくない側面と、人間の側に立って邪悪なものを追い払う好ましい側面を感じ取ってのではないでしょうか。それを人間生活に役立たせると考えていたようです。
いま日本には三十万個以上の鬼面瓦が屋根の上から私たちのくらしをみつめています。鬼瓦は最もポピュラーな鬼であり、強い守護神としての願いをこめた鬼です。



0 件のコメント:
コメントを投稿