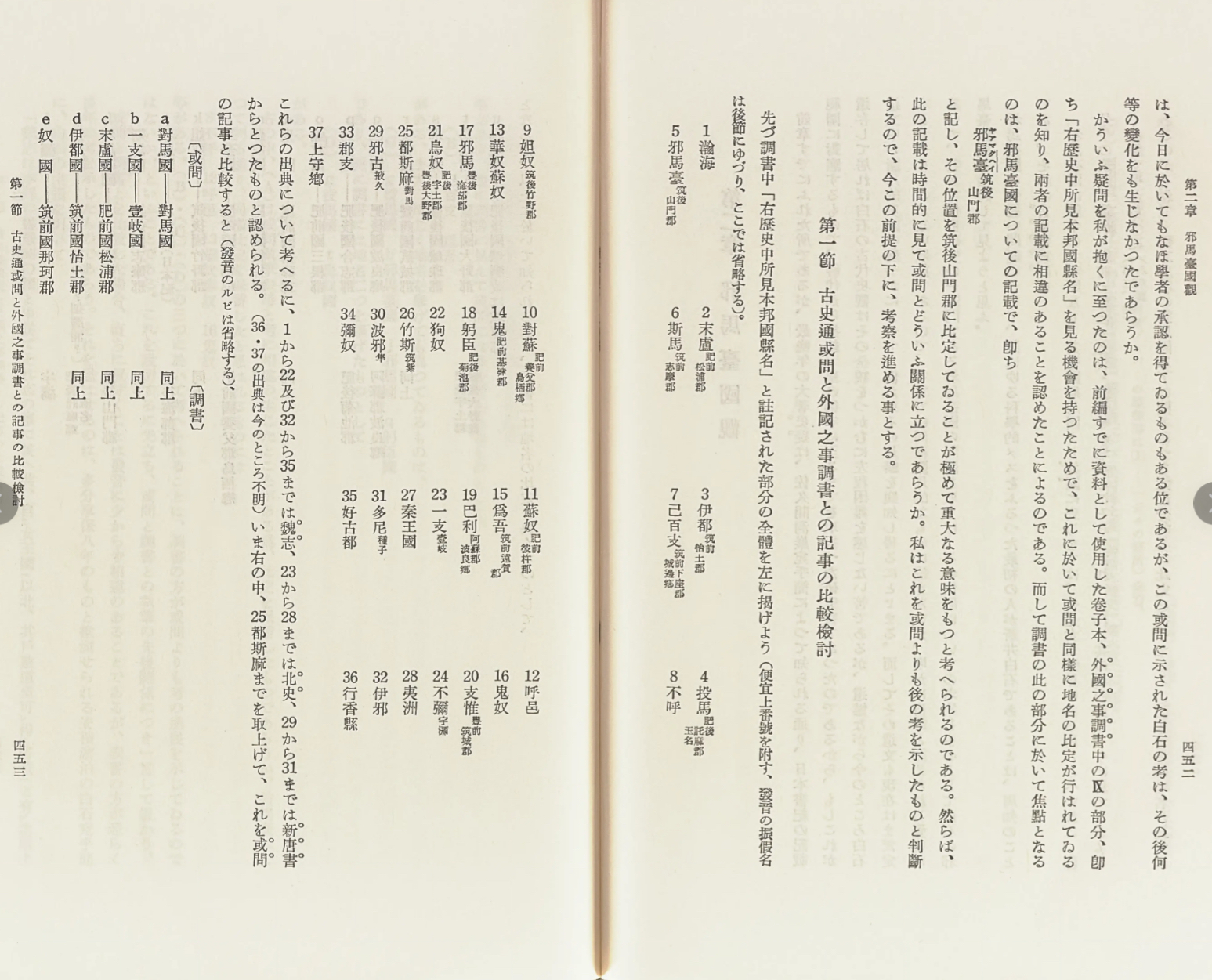信長に先んじた天下人・三好長慶の軍事拠点か 櫓備えた「西院城」とみられる遺構が初出土
「織田信長に先駆けた天下人」と呼ばれ、その重要性が再評価されている戦国武将、三好長慶(ながよし)(1522~64年)が京に確保した軍事拠点「西院(さいいん)城」とみられる建物と溝の跡が、京都市右京区の阪急西院駅近くで出土したことが分かった。西院城は文献や絵図には登場するが、具体的な遺構が見つかったのは初めて。遺構からは、覇権を激しく争った「元祖天下人」らしい強気の姿勢もにじみ、関係者は「長慶の強権ぶりを知る史料」と評価する。 ■義昭上洛に合わせ焼失 西院城は、現在の西大路四条交差点の西に広がる小泉荘を基盤とした小泉氏が築き、長慶が16世紀中ごろ、室町幕府の将軍補佐役だった細川晴元と対立する中で城をさらに強化した。当時、京内に戦闘用の城が築かれるのは珍しく、唯一だったとの見方もある。 公家・山科言継(ときつぐ)の日記には天文19(1550)年4月、晴元が西院城を攻めたとの記述が残る。長慶死後の永禄11(1568)年、信長が後の15代将軍・足利義昭とともに上洛するのに合わせ、三好氏配下の小泉氏側が抵抗の意はないと自ら城に火をかけ、以後は再建されることはなかったという。 ただ、焼失後の天正2(1574)年、信長が上杉謙信に贈ったと伝わる狩野永徳作の洛中洛外図屏風(びょうぶ)(国宝)の中にも、「さいのしろ」の名で焼失前の西院城が登場する。 今回、民間団体の平安京調査会(京都市)が西大路四条交差点の西約300メートルに位置する共同住宅の建設予定地約180平方メートルを調査したところ、格子状に柱が立つ総柱建物と石組み溝の跡が出土した。一緒に出た土器などから長慶が活躍した時期の遺構と判明したという。 平安京調査会の吉崎伸調査部長は「町家とは雰囲気の違う大きな礎石を持った建物跡で、すぐに西院城のものだと分かった」と振り返る。 ■大型の礎石「高い建物が存在」 建物の規模は東西8・3メートル、南北4メートル。中央部の東西2・5メートル、南北4メートルは床張りで、東西両側に土間を配した特異な形であることも分かった。柱の礎石は地下式で0・6~1・0メートルと比較的深い場所に据えられ、中には0・4メートルを超える大型の石もあった。 吉崎部長は「柱が地下の深いところに届き、柱を支える礎石も大型。地上には櫓(やぐら)のような高い建物が存在していたとみられる」と推測した。