『阿波国風土記』(「好字二字令」と『古風土記』)
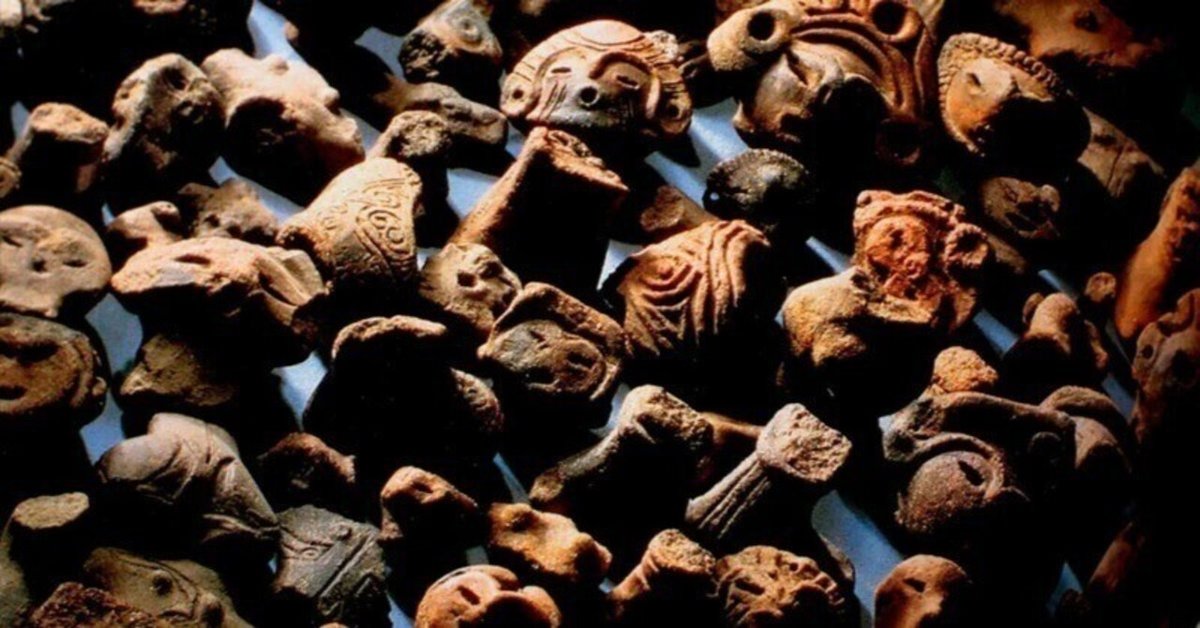
1.「好字二字令」(『風土記』編纂の勅命)
(1)「好字二字令」
「好字二字令」は、元明天皇の御世、和銅6年(713年)5月2日に発せられた勅令である。「諸国郡郷名著好字令」「好字令」とも呼ばれ、全国の「国名」「郡名」「郷名」を、好ましい漢字2文字にしろという命令である。これにより、国郡郷名は漢字二文字に統一された。
(例)「吉備道中国」は「備中国」、「粟国」は「阿波国」に改名。
・国郡郷名以外の地名も漢字2文字に変えられることが多かった。
・三文字地名は、「好字二字令」以前の古地名だという。
五月甲子。制。畿内七道諸国郡郷名、着好字。其郡内所生。銀銅彩色草木禽獣魚虫等物。具録色目。及土地沃塉。山川原野名号所由。又古老相伝旧聞異事。載于史籍亦宜言上。
(五月甲子。畿内七道、諸国の郡、郷の名には、好(よ)き字をつけよ。其の郡内に生ずる所の銀、銅、彩色、草木、禽獣、魚、虫等の物は、具(つぶさ)に色目を録せしむ。及び土地の沃塉、山、川、原、野の由来する所の名、また古老の相伝、旧聞、異事は史籍に載せ亦宜く言上すべし。)
(2)『風土記』編纂の勅命
この「好字二字令」は、「『風土記』編纂の勅命」でもあった。
というのは、「好字二字令」により、「粟国」は「阿波国」に改名されたわけで、
①「粟国」を「阿波国」に改名したという報告が欲しい。
②「粟国」であれば、「粟が生い茂る国」だと想像できるが、「阿波国」に改名したために想像できなくなったので、地名の由来を知りたい。
ということで、『風土記』の編纂と提出が命じられたという。
求められた『風土記』の内容は、
①新しい国郡郷名
②産物
③土地の肥沃の状態
④地名の起源
⑤伝えられている旧聞異事
であった、
(3)『古風土記』
『風土記』には何種類もあるので、最も古い和銅6年の『風土記』を、便宜上、「古風土記」と名付ける。
現存する「古風土記」は全て写本で、
・『出雲国風土記』は、ほぼ完本が現存
・『播磨国風土記』『肥前国風土記』『常陸国風土記』『豊後国風土記』が一部欠損した状態で現存
であり、他国の古風土記は、後世の書物の「逸文」(引用文)のみである。この逸文の中には、本当に古風土記の記述の引用であるか疑問が持たれているものも存在するので、注意を要する。
2.『阿波国風土記』
(1)都市伝説
明治元年には、『阿波国風土記』を徳川家と蜂須賀家が所有していたが、現在は行方不明である。
都市伝説①記紀と異なる記述があったので、明治政府が回収
→関東大震災で焼失
→宮内庁が秘匿
都市伝説②徳川家と蜂須賀家が所有していた写本以外の写本がある。



0 件のコメント:
コメントを投稿