参考:
ダルマと使徒トマス
https://freeassociations2020.blogspot.com/2021/09/blog-post_92.html
レムナント2018/04
典である。インドの高名な宗教学者アーマンド・シャー博士は、
「キリストの使徒トマスの福音に対抗して、シャカを聖人から救い主に昇格させたのが大乗仏教である」と述べている。
28頁
Armand Shah
不明
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E6%9D%91%E8%8A%B3%E6%9C%97
freeassociations: 「法華経と聖書」久保有政の今月のレムナント 2022年12月
https://freeassociations2020.blogspot.com/2023/01/202212.html
| ||||||||||||||||||||||||
https://x.com/slowslow2772/status/1789986748849660006?s=61
https://x.com/slowslow2772/status/1870755067856564444?s=61
| ||||||||||||||||||||||||
第4章 聖トマス、インドへ行く

トマス伝説
トマスといえば聖書にその記述が少なく、十二使徒のなかでももっとも地味な存在なのに、インドのクリスチャンが多い地域では英雄のごとき聖人である。これはどうしてだろうか。
伝説によれば、トマスはイエスによってインドに派遣され、福音を広めたのだという。西暦52年、トマスは現在のケララ州に上陸し、シリア正教会の基礎を創設するが、西暦72年に狂信的なバラモンによって殺され、殉教者となった。
イエスのインド修行伝説を語るにおいて、トマス伝説を無視することはできない。聖トマスがインドに来たという伝説があったからこそ、イエスのインド修行伝説もまた生まれたのだ。
エルサレムではイエスのもとに十二使徒が集まり、それぞれに布教の担当区域が割り当てられた。キリスト教の登場が画期的であったのは、布教に力点が置かれたことだった。真偽のほどはともかく、イエスと十二使徒の時代から布教の戦略が練られていたとしても不思議ではない。
布教区域の割り当て(表はM・M・ニナンによる)
◇シモン・ペトロ パルティア(ポントス、ガラテヤ、カッパドキア、アジア、ビテュニア) ブリテン
◇アンデレ カッパドキア ガラテヤ ビテュニア スキタイ
◇熱心党のシモン 北アフリカ ブリテン
◇アルファイの子ヤコブ スペイン
◇ディデュモスのトマス パルティア メディア ペルシア 北西インド
◇バルトロマイ パルティア メディア ペルシア 北西インド
◇ユダ アッシリア メソポタミア
◇フィリポ スキタイ 小アジア北部
◇マタイ パルティア ヒンドゥークシ
◇ヨハネ ガリア(フランス)
◇ヤコブ(ヨハネの兄弟) ヘロデ王により斬首
◇マティア ダキア(ルーマニア) マケドニア
◇パウロ 小アジア南部 英国諸島
このなかでももっとも人口に膾炙しているのがトマスのインド布教である。それはエデッサのグノーシス主義者バルダイサン(154-222)によって書かれたとされる新約聖書外典『トマス行伝』がよく知られているからだ。
この図にあるように、インドで布教する前、聖トマスはパルティアなどで布教活動をしていた。
1656年、聖トマスについて調査するためにローマ法王はカルメル修道会のヴィンチェンゾ・マリア神父をインドへ派遣した。マリア神父によれば、トマスのミッションはシリアからメソポタミアにかけての地域ではじまっていた。そしてその後はるか東の中国西安にまで足を伸ばしたという。それから聖トマスはふたたび中東にもどる。その後なんとブラジルへ行き、また戻ってエチオピアを訪ねたあと、アラビア半島の沖合にあるソコトラ島(現イエメン領)に渡った。インド南部にたどりつくのはようやくそのあとのことだった。まずマラバル海岸で福音を伝え、コロマンデル海岸(マドラスとマイラプール)へ移動したあと彼は殉教者となった。
この最初に行ったシリアからメソポタミアにかけての地域とは、パルティア国の領土だった。そこでトマスはパルティア人、メディア人、(アフガニスタン北部の)バクトリア人、(カスピ海の)ヒュルカニア人、(スリランカの)タプロバニア人などのあいだでキリスト教を説いたのだという。
およそ真実味が欠けてはいるものの、ヴィンチェンゾ・マリア神父は広範囲にわたって神話や伝説を収集したのだろう。実際に使徒トマスがインドをはじめとする世界各地を遍歴するというようなことがなかったとしても、これだけの神話・伝説が生まれるための何かがあったのはまちがいない。
トマスが布教活動の拠点としたシリアのエデッサ国(現在のトルコ領ウルファ)は、アブガル王(13-50)とイエスの往復書簡で知られる。しかし実際にトマスの使者アッダイと会ってキリスト教徒となったとされるアブガル王は、アブガル9世だったようだ。エデッサの王が改宗するのはトマスよりずっとあと、百数十年後のことなのである。その後エデッサは東方諸教会の中心地となっていく。東方諸教会に分類されるインドのシリア正教会(マランカラ・シリア正教会とヤコブ派シリア教会)と強いつながりがあるのは当然のことだった。
トマス伝説は、キリスト教のなかでも、ネストリウス派やシリア正教を含む東方諸教会の伝播と関係があるようだ。
トマスがパルティア国内で布教活動をはじめたのは西暦30年頃だとされ、インド南部に上陸したのは西暦52年である。ケララの伝承によれば、このずっと前、西暦40年頃にガンダーラの中心地タクシラにトマスは来ている。ここで『トマス行伝』に登場するインド・パルティア国の建設者グンダファル王(ゴンドファルネス)と会っているのだ。王の話す言語はギリシア語だったという。
M・M・ニナンによれば、西暦46年頃には、テュアナのアポロニオスもグンダファル王と会っている。タクシラはインド北部のキリスト教布教の中心地となるが、クシャーナ朝になると早くも潰えてしまった。カニシカ王の時代(2世紀)、ガンダーラ仏教が隆盛を見るのである。
インド南部に行く前、船が難破してしまったのか、聖トマスは竜血樹で知られるソコトラ島に漂着する。上述のようにソコトラ島は現在イエメン領である。トマス伝説の真偽はともかく、ソコトラ島の住人はキリスト教徒だった。ソコトラ(Socotra)という島の名はどうやら祝福の島を意味するサンスクリット語のドゥヴィパ・スカダラ(dvipa sukhadhara)からきているらしい。
10世紀、アラブの地理学者アブ・ザイード・ハッサンは島の住人はネストリウス派だと記した。
1294年にソコトラ島に立ち寄ったマルコ・ポーロは、住人がキリスト教徒だったと証言している。
1435年にソコトラ島にやってきたニコロ・コンティは、「島はアロエを産し、住人はネストリウス派のクリスチャン」と記した。
フランシスコ・ザビエルは1523年にこの島を訪ね、住人が「名ばかりのクリスチャン」であることを指摘した。彼らは洗礼の仕方さえ知らなかったので、ザビエル自身が子供たちに洗礼を施したという。
しかし1683年にヴィンチェンゾ・マリア神父は「キリスト教徒は絶えてしまった」と報告している。
千数百年も守られてきたキリスト教の灯は永遠に消えてしまったのだ。
西暦52年、トマスが乗った船は現在のケララ州コドゥンガルール(コーチの北)に着いた。伝承によれば、現代まで残るインドのキリスト教はこの時期にまでさかのぼることができるのである。
しかしインドのトマス派キリスト教徒が伝えてきた『トマス行伝』の舞台は南インドではなく、北西部の(現在はパキスタンの)タクシラだったようだ。ただし文中では国の都であることをほのめかすだけで、場所を特定しているわけではない。『トマス行伝』は際立ったエピソード満載の魅力的な物語であり、キリスト教の教義のようなものはあまり感じさせない。一種の大衆小説のようなものと考えればいいのかもしれない。
マールガム・カリ〜キリスト教徒の輪舞
はらみつ展2024 おまもり
13時〜19時(最終日のみ17時まで)
@(池ノ上/下北沢)
木彫・刺繍・顔彩等 パロミタ友美がおまもりとして作ってきた作品たち

本人達に訊いたら、「え、そんなに少ないの?」と言われそうです。
ケーララには、かなりの数の教会があります。
現在、その多くはポルトガル宣教師以来のラテン系カソリック教会…
と思いきや、実は最も多いのは、そのずっと以前から続く東方シリア教会系。
ケーララのキリスト教には、意外なほど長い歴史があるのです。
ここで紹介するのは、そんなケーララ・クリスチャンの踊りです。
聖トマスが宣教した?
西暦52年、この地に使徒トマスが降り立った、と言われています。
よくある眉唾ものの話に聞こえるのですが、
実は当時、アラビア海を挟んでローマ帝国と、インド西南のケーララ地域の交易が盛んで、
むしろその後の千五百年間よりもずっと、当時は
パレスチナからインド西海岸に渡りやすい状況にあったそうです。
ウィリアム・ダルリンプルによると、
シナイの6世紀の教会で発見された「聖トマスの行い」という文書には、
「イエスの死後、使徒トマスはゴンドファレス王に招聘された」と書かれています。
十九世紀末になると、この王の名「ゴンドファレス」が刻まれた貨幣が発見されました。
ペルシャ系(パルティア)のこの王は、
紀元19年から45年まで北西インドを統治をしたということで
一気に聖トマス来訪説の信憑性が高まったのです。
ちなみに「トマス」という名のアラム語の原義は「双子」であり、
この文書には実際、トマスがイエス・キリストの双子であった、とも記されています。
尚、「ゴンドファルネス」の名は現在、複数の王に冠されていたことが確認されています
(英語ウィキ/日本語ウィキ…ただしこちらは出典の明記が無い)。

使徒トマスが実際にケーララで宣教活動を行ったかどうか
については、今も論の分かれるところですが、
彼の同時代人がインドでキリスト教を布教したことに関しては、
概ね認められているようです。
どのように始まったのであれ、その後ケーララのキリスト教徒たちは
シリア正教会と合流し、多数派とはならないまでも、
それなりの力を蓄えつつ生き延びてきました。
現在、キリスト教は西洋と同音異義語のようにも語られていますが、
歴史を辿ってみれば、中国で「景教」とも呼ばれていたように、
あるいは日本で「隠れ切支丹(キリシタン)」が独自の信仰をひっそりと育て守っていたように、
仏教顔負けのグローバル・バラエティを有していたのです。
そもそも当初は、ローマ帝国に迫害されていた、ユダヤ教から派生した一派でした。
現在も、日本ではあまり知られていないというだけで、
種々の伝統や教派が存在しています。
そういう訳で、ケーララにはキリスト教徒に伝わる民俗芸能もあります。
それがマールガム・カリ(道のりの遊戯)です。
クリスチャンの輪舞「マールガム・カリ」
15世紀、ヴァスコ・ダ・ガマの上陸以降、ポルトガルの宣教師たちがインドに入って来ました。
「土着」のキリスト教はやがて弾圧され、
関わる資料もほとんどは灰に帰されてしまったということで、
余計に過去のケーララ・クリスチャンの歴史は謎に包まれているのです。
現在伝わるマールガム・カリは、途絶えかけていた伝統が
何度も再興されてきたという、歴史と努力の賜物です。
(ダルリンプルは、途絶えかけた「マラバールの踊る尼僧たち」の復興の動きについて記していますが、これは恐らくマールガム・カリの事でしょう。)
ティルワーティラカリから派生したとも、
ユダヤ教の結婚式の踊りから派生したとも言われています。
主に使徒トマスの宣教の旅について歌われており、
かつては男性のみの踊りだったそうですが、現在はむしろ
女性によって踊られることが多い踊りです。(ソース:ウィキ)
クリターラム(と思われる、歌い手が使っている小さなシンバル)の使用や
ジャティ(リズム言葉)を旋律に乗せている事、
途中で二人一組になるような振り付けなど、
ケーララ民俗芸能の特徴が見られます。
手の動きなども、非常にケーララらしいです。
この動きの激しさをもって、私のマラヤーラム語の先生は、
これを元々のケーララの芸能だとはあまり感じていないようでした。
しかし、これはあるいは、元々男性によって踊られていたから、
ということもあるのかもしれません。
対して、ヒンドゥー系土着のティルワーティラカリは、
昔から女性によって踊られていて、より女性らしい動きです。
次の動画は少年たちによるマールガム・カリです。
これを見ると、やはり、マールガム・カリは元々、
男踊りの系統なのかな、というふうに感じます。
舞踊劇カタカリでも、男役の動きと女形の動きが違っていて、
女形の動きはモヒニヤッタムにも通じる優雅さがあります。
編成こそティルワーティラカリという、女性たちの踊りにそっくりなのですが、
元々男性のみの踊りだったという歴史が、動きに出ていると考えるとしっくり来ます。
ちなみに、中央のオイル・ランプ。
これ自体はケーララの伝統的なとても一般的なものですが、
ここでは形が聖トマス・クリスチャンのシンボルになっています。
こちらの記事が気に入ったり、お役に立ったり、何か琴線に触れるものがあれば、よろしければ投げ銭でサポートをいただけると嬉しいです。ジョイグル
最初に、パロミタの自伝シリーズが11回に渡り配信されます。
もちろんお時間無いときはスルーしてくださいね、という前提なのでお気軽にどうぞ。
http://mikiomiyamoto.bake-neko.net/bookreview0244.htm
ヒンドゥー教から見た聖トマス
ここまではトマス派のクリスチャンの視点から聖トマス伝説を眺めてきた。彼らにとってトマスは十二使徒のなかでも特別なひとりであり、イエスの双子の兄弟であり、1世紀半ばにパルティアからインド、そしておそらく後漢朝の中国にまで布教活動の範囲を広げた聖人なのである。
しかしキリスト教徒以外の人々、とくにヒンドゥー教徒からすると、トマス伝説はナンセンスな作り物だった。
コエンラード・エルストはつぎのように述べる。(『聖トマスの神話とマイラプール・シヴァ寺院』)
実際、この使徒(トマス)がインドに来たという事実はなかった。南インドのキリスト教共同体は西暦345年、トマス・カナエウスという商人によって作られたものだった。(この名前からトマス伝説も生まれた) 彼は400人を率いて弾圧を強めるペルシアから脱出した。そしてインドで当地の支配者から庇護を受けたのである。
ヨーロッパのキリスト教大学ではもはや使徒トマスがインドへ行ったという伝説が歴史として教えられることはない。しかしインドではいまだに歴史として扱われることがあるのだ。重要な点は、トマスが受難者として持ち上げられ、(トマスを殺した)バラモンが狂信者として非難の対象となることである。
ヒンドゥー教徒がトマスを受難者として認めないことに、宣教師たちは憤懣やるかたない、といったように見える。(流れた血は信仰の種とみなされる) それゆえ彼らはストーリーを作りださねばならなかった。彼らは狂信的なヒンドゥー教徒の手にかかって殉死した聖トマスを記念して教会を建てたというが、実際は反対で、狂信者に殺されたのはヒンドゥー教徒だったのである。ジャイナ教寺院とシヴァ派寺院は強制的にキリスト教会に変えられた。マイラプール海岸から異教徒を一掃すると称して、キリスト教の兵士たちがどれだけのバラモンやヒンドゥー教信者を殺したか、多すぎてだれにもわからないのだ。
このように憎悪の念に満ち溢れている。聖トマスがインドに来たという事実がなかったどころか、4世紀以降キリスト教がインドで布教される段階で、多くの流血の惨事があったというのである。
そうすると、聖トマスが中国へ行ったという伝説もまったく信憑性がないということになる。とはいえ、とくに唐代、ネストリウス派(景教)の布教がさかんでかなりの信者を獲得したのはまちがいない。数百年のずれがあるのだ。シリア教会はネストリウス派の流れをくむ東方諸教会の教派であり、唐代の中国で布教した人々とインドで布教した人々が同一であった可能性はあるだろう。
http://mikiomiyamoto.bake-neko.net/bookreview0243.htm
トマスの歌
ケララ州のトマス派キリスト教徒にあいだには、聖トマスが来た1世紀から口承で伝えられてきた歌がいくつか存在する。トマ・パルヴァム(トマスの歌)はそのうちのひとつだ。聖トマスによって任命された初代司教の後裔であるトマス・ラムバーンが、1601年にはじめて書き留めたのだという。
トマスの歌
私は歌おう。
どのような道をたどって聖なる教えがマランカラにもたらされたかを。
使徒トマスは、商人ハバンとともにマリアンカラに上陸した。
そこで奇跡を起こし、8か月の間にイエス・キリストの教会を創設した。
そしてマイレプラム(マドラス)へ行った。
そこでトマスは4か月半の間、福音を説いた。
そして船に乗って中国へ向かった。
トマスは4か月半の間中国に滞在し、マイレプラムに戻ってきた。
およそ1か月の滞在中、
ティルヴァンチクラムの王(ラジャ)の義理の息子がトマスのもとにやってきて
マラバルに戻るよう請うた。
彼らは船に乗ってマリアンカラに着いた。
使徒はそこで6か月以内に
ラジャ、その家族、40人のユダヤ人、400人の人々を改宗させた。
トマスは人々に教えを説き、十字架をかかげる教会を建て、司祭を任命した。
最初に任命したひとりはラジャの義理の息子で、名をケパと言った。
ケパとともにトマスはキロンへ行き、
十字架を打ち立て、2400人に洗礼を施した。
キロンから彼らは山中のチャヤルへ向かった。
キロンにはまる一年滞在し、2800人に洗礼を施した。
トリパレスワラムの支配者の要望により、トマスはその村へ行った。
ところが人々が十字架を汚しているのを見て、その土地を呪った。
しかしそれでもトマスは2か月間そこに滞在した。
彼はもう一度十字架を建て、人々に教えを説いた。
それゆえトマスはふたたび異教の地へ赴く必要がなくなった。
トマスという男を司祭に任命した。
信仰心のあるリーダーである。
2か月の間、トマスはトリパレスワラムに滞在した。
彼はすべてのキリスト教徒の信仰心を強め、200人の異教徒を転向させた。
そこから遠くない南方の地に
彼はニラナムの教会を建てた。
彼はそこで生まれたトマス・マリエカルを司祭に任命した。
それからコッカマンガラムへ行き、1年間滞在した。
そこで彼は1500人を転向させ、十字架を建てた。
また人々に神への崇拝の仕方を教えた。
トマスはまたコッタカヴ・パルルへ行き、1年滞在し、2200人を転向させた。
そこから彼は南のルートをとり、マリアンカラに戻ると
驚くべきことにキリスト教徒の共同体が花開いていた。
そこへの滞在は2週間にとどめ、北方のパラユルへ行った。
そこに1か月滞在し、1280人に洗礼を施し、十字架を建てた。
その年(西暦59年)の終わり、トマスはマイレプラムに戻った。
彼はもう一度マラバルに戻った。
旅の間トマスは天使に守られた。
彼は2か月間マレアットゥルに滞在し、220人を転向させた。
ニラナムには1年滞在し、人々の信仰心と彼らの送った人生に満足した。
彼らは聖蹟を得ていなかったので、トマス自身が人々に聖餐を与えた。
そしてトマスは人々に別れを告げ、タミルの地へと旅立った。
トマス・ラバンとラジャの義理の息子ケパはしばらく先まで見送った。
われらの聖者がどれほど多くの奇跡を起こしたか、述べることはできない。
トマスは29人の死者を蘇らせた。
悪魔に取りつかれた250人を救った。
330人のらい病患者を癒した。
250人の盲目の人の視力を戻した。
120人の足萎えを歩けるようにした。
20人の聾唖者の聴力を戻した。
医者に見捨てられた280人の病人の病を治した。
トマスによって17490人のバラモン、350人のヴァイシャと農民、
4289人のシュードラがキリスト教徒に転向した。
彼は2人の司教、7人の司祭を任命した。
そのうち4人はラバンと呼ばれた。
また21人の助祭を任命した。
*「トマスの歌」は1892年、バルゲス・パラユルによって作られ、1916年にトラバンコールのベルナール神父によって出版されたという。(イシュワル・シャラン
インドで殉教した使徒トマスの伝承および「トマス福音書」についての個人的なコメント
2009年に南印度の新興都市バンガロールに行ったときに、当地のカトリック・カルメル会の司祭から、使徒トマスがインドに布教し、その地で殉教したという伝承をインドのキリスト者は非常に大切にしているということを聞かされて、さもありなんと大いに頷いた事があった。
たとえば、バンガロールにあるカルメル会の修道院には、「瞑想する使徒の画像(それはヒンズー教のヨガ行者・座禅する仏陀とよく似ていた)」が、講堂の壁画として飾られていた。ちょうどローマのサンピエトロ寺院が使徒ペテロの殉教の場所に立てられたのと同じように、インドのキリスト者にとっては、使徒トマスの殉教(これはトマス行伝にある)の地、インドで彼のキリスト教を継承するという考え方は自然なのである。
西洋諸国のキリスト教宣教が、帝国主義・植民地主義と深く結びついていたことは言うまでも無かろう。ところがインドにはスペイン人やイギリス人がキリスト教を伝道する遙か以前から、直接に使徒繼承のキリスト教が伝えられていたのである。したがって、インドではローマ典礼以前にシリア典礼に従う礼拝が行われていた。そして、インドのキリスト教徒の数は、ヒンズー教に比べれば少数派であるとはいえ、仏教徒の数よりも多いのである。
さて、福音書といえば西方に伝えられたキリスト教では、ローマカトリック・プロテスタント・ギリシャ正教をとわず、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの4つが聖典であって、トマス福音書なるものの存在を知らない人の方が多いのではないだろうか。我が国でも、基本的にキリスト教といえば西洋のものと考えるものが多いから、トマス福音書の存在を知っている人でも「外典」として、軽んじている人が多かったと思う。
西洋ではトマス福音書はグノーシス主義(信よりも自己認識を重んじるキリスト教)として異端視され、それを否定する論者の引用を通じてのみ知られていたのである。しかるに1945年にエジプトのナグハマディで、コプト語に翻訳されたトマス福音書のイエス語録が発見されるに及び、事態は大きく展開した。ナグハマディ文書の発見はある意味で摂理的な出来事であったのではないか。
私は、インド旅行から帰ってから、荒井献氏の懇切なる注解のついた「トマス福音書」を読み、その内容に深く感銘した。この5番目の福音書を読めば、4福音書のイエスのことが更に良く分かるであろうし、西方に伝えられたキリスト教では切り捨てられたイエスの教えの大切な内容を知ることが出来るという確信を得たのである。
西方に伝えられたキリスト教は、率直に言ってその教義の本質に帝国主義的な所がある。唯一の神は絶対的な創造主であって、全能であり、万物を支配する「嫉む神」であり、他の神々や人間が自分と等しい存在となることを許さぬ我が儘な独裁者の如き存在である。トマス福音書は、このような宇宙を支配する気まぐれな創造主を究極のものとは見ない。「嫉む神」にまさる至高者から遣わされたイエスは、その至高者を知り、それと一つである存在である。
この世の専制君主として君臨している「神」は、実は自己を知らぬ未だ「無知」なる存在であり、イエスはそのような神以上の存在である。そしてイエスを先覚者としてイエスに倣う人間はだれでも自己の本質を認識することによって、イエスと同じ存在になることができる。
トマス福音書では、使徒トマスはこの意味で、イエスの生き方を自らのものとして、イエスをもっともよく理解した使徒であり、精神的なる意味でイエスの「双子」と呼ばれる。トマスとは「双子」という意味である。マタイによる福音書では、ペテロがイエスの後継者としてローマ教会の鍵をゆだねられたが、トマス福音書ではトマスこそ、イエスの心をペテロ以上に知る使徒として描かれている。
人は自己が何ものであるかを認識したときに神を認識できるという思想は、アウグスチヌスにも見られるものであり、決して異端などではない。むしろ、絶対者として万物の上に君臨する神の観念のほうが、一神教の名前を借りた偶像崇拝であるといえるのではないか。このような偶像崇拝が人間を如何に抑圧し、どれほどひどい異端審問・宗教戦争を人類にもたらしたかを思えば、今日の世界に於いて、西方キリスト教の神学の中でイデオロギーとして絶対化された神よりも、トマス福音書のイエスの言葉の方に人々は共感するのではないだろうか。
「イエスは言われた、「汝等を導くものが「見よ、御国は空にある」というならば、空の鳥が汝等に先んじるであろう。「御国は海にある」といえば、魚が汝等に先んじるであろう。そうではなくて、御国はまず汝等の内にあり、次に汝等の外にあるのだ。汝等が自己自身を知るときに、汝等は知られるのであり、生ける父の子等であるのは汝等であることが分かるであろう。しかし、汝等が自己自身を知らぬならば、汝等は貧困のうちに住むのであり、その貧困こそが汝等なのである。」(トマス福音書 イエス語録3)
トマス福音書については、聖書学者の研究がこれから数多く為されるであろうが、現在の段階でのわたしのコメントを纏めておきたい。
序と第一のロゴス
これらは隠された言葉である。これを生けるイエスが語った。そしてデドモ・ユダ・トマスが書き記した。そして彼が言った、「この言葉の釈義を見出すものは死を味わうことが無いだろう。」
コメント
「隠された言葉」(オクシュリンコン・パピルスのギリシャ語断片では、ホイ・ロゴイ・アポクリフォイとある)は、一般の読者に「公開された教え」ではなく、イエスと親しく霊的な交わりを持ったものに「霊的に啓示された内面的な教え」であるという意味であろう。
日本では、「アポクリファ」を「外典」と訳すことがあるが、これは「正典」の「外」の文書という意味であるから、「アポクリファ」を正典にいれなかった当時の公教会の立場を前提した翻訳である。アポクリファを大切な伝承として保存してきた人々の立場からすれば、公教会の「正典」が「顕教」であるならば、アポクリファは「密教」と訳すべきであろう。そして「密教」の立場からすれば、それは、「生けるイエス」が我々の心の奥底で語った言葉であるが故に、「顕教」よりも深い教えなのである。
次に問題とすべきは、「生けるイエス」の解釈である。顕教の立場からすれば、これは「復活したイエス」の言葉である。前掲の荒井献の著書を読んだが、彼の解釈はグノーシス的であった。つまり、そもそもイエスは不死であり、十字架上での死は、単なる肉に於ける死であり、それは、信者を救うための方便であった。本来、神の子イエスは「永遠に生きている」のであり、死ぬことはない。そして、語録第一では、生けるイエスの言葉を釈義するものもまた、死を味わうことのない本来の自己を見出すであろうと、明言している。
「釈義」とはギリシャ語断片では「ヘルメーネイア」である。ヨハネ福音書の並行箇所と比較したい。そこでヨハネはわたしの言葉を守るものは、永遠に死を見ないであろう。(ヨハネ福音書 8-51) と言っている。「守る」と「釈義」の違いについて荒井献は、「ヨハネ福音書ではキリスト論が人間論に先行するが、トマス福音書では、人間論がキリスト論に先行する」と言っている。つまり、人間が真に人間となるためには、ロゴスの受肉、イエス・キリストの死と復活を信じ、イエス・キリストの言葉を守ることが必要であり、かくして初めて、人間は、永遠の生命に到るというのがヨハネの神学だというのである。これ対して、トマスの神学では、イエスの言葉の正しい解釈を通じて、我々は、我々自身の「本来の自己」が不死であることを自覚するのである。つまり、本来の自己を認識したものは、イエスと霊的な意味で「双子」なのであり、覺知をもたらしたもの(イエス)と、イエスの言葉を通して自己を認識したものは、同じ「覚者」なのである。
荒井献のトマス福音書解釈に対して、私は、暫定的ではあるが、次のような私自身の解釈を対比させよう。それは、グノーシス的解釈をその方向にさらに突破したような解釈をめざすものである。
使徒トマスの立場でも、「釈義(ヘルメーネイア)」は単に知的に理解することではなく、その言葉によって生きることを意味しているのではないだろうか。それが我々の本来の自己の何ものであるかを教えるものであるといっても、その覺知(グノーシス)は、イエスの行いと十字架の死、復活という出来事によって、初めて弟子達に自覚されたのである。イエスが「一粒の麦」として死ななければ、弟子達は、彼らの本来の自己が何ものであるか、つまり自己が神の子であることを自覺しはしなかったであろう。本来の自己の自覚は、旧き自己に死ぬという絶対否定無くしてはありえない。その絶対否定を通じての復活ということを、弟子達は「十字架のイエスと共に死し、その復活に与る自己」として自覚したのである。
たんなる知性認識が、「覺知のキリスト教」の「覺知」なのではない。知性認識を越える「覺知」が宗教経験にとっては不可欠である。そういう「覺知」を私は、「グノーシス」などという手垢にまみれた言葉ではなく、西田幾多郎の言葉を援用して、「メタノエシス」あるいは、「ノエシス的超越」と呼びたい。そして田辺元が指摘したように、ノエシス的超越(メタノエシス)とは、メタノイア(懺悔=他者に対する罪の自覚)を本質的に伴うものでなければならない。「自覚」は「他者に対する罪」の自覚を伴わなければ「本来の自覚」ではないのである。それこそが、「キリスト教的自覚」の特色ではないか。
人間論とキリスト論との関係という問題は、確かに、トマス福音書とヨハネ福音書の神学を比較する上で、きわめて重要な論点であるが、トマスもまた復活のキリストを受け入れたが故に、ペテロと同じく困難な伝道の旅に出て、インドで殉教したのである。だから、決して、荒井が言うように「トマス福音書では、一般的な人間論がキリスト論に先行する」などとは言えないのである。そうではなくて、ヨハネ福音書とトマス福音書の違いは、おそらく、トマスの理解した「復活」とは「霊における復活」であり、これに対して、ヨハネ福音書が強調するのは、「肉体を伴った復活」であったのだろう。
それゆえに、ヨハネ福音書の中では、肉体を以てイエスが復活したことを信じようとしない(不信の)トマスにたいする言及(ヨハネ20:24-29)がある。トマス福音書の冒頭部分だけでも、実に重要な聖書解釈上の問題、そして單なる解釈問題だけではなく、「イエスの言葉を守ること、それによって生きる」とはいかなる意味であるのか、キリスト者にとって本質的な問題を再考させてくれることは間違いない。
使徒トマスの伝説「聖十字の丘の上の教会」- インド文化圏の音楽(13)
映画「Bajrangi Bhaijaan」から「Tu Jo Mila」のつづき。
歌詞から
| 君の神を探していたら、私の神を見つけた Dhoondte tera khuda mujhko rab mila Looking for your God, I found my God |
「神/khuda/rab」について。
「khuda」はペルシャ語の「神」で「Lord」や「God」という意味。
(イラン・ペルシャ地方の宗教)
| 意味 | 宗教 | 神の名前 |
|---|---|---|
| 「Lord」(支配主) | ゾロアスター教 | 最高神アフラ・マズダー (Ahura Mazdā) |
| 「God」(創造主) | イスラム教 | 唯一神アラー |
「rab」はアラビア語の「神」で「Lord」や「God」という意味。
パンジャブ地方は土地柄もあってペルシャやアラブから言葉の影響も受けているようです。
| セム語族(橙色) |
|---|
 |
| By Listorien [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons |
ヘブライ語の「רב rav」は「master」(師)で、ユダヤ教の宗教的指導者「ラビ/rabbi」は「わが師」という意味になるようです。
そこでユダヤ人宗教指導者イエスです。
そのイエスの使徒トマスが、西暦50年ころにインドにやって来て、現在のケーララ州からタミル・ナードゥまでを布教したという話があります。
今のところ確実な証拠は見つかっていないけれども、当時ケーララのコーチンにコーチン・ユダヤ人という人たちが住んでいたらしいし、西暦40年~70年ごろ(推定)成立の「エリュトゥラー海案内記」では、ローマと南インドの貿易の様子が書かれていて、人の往来はあったようです。
| 「エリュトゥラー海案内記」に登場する地名、航路、交易品 |
|---|
 |
| By George Tsiagalakis [GFDL or CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons |
今回の歌はケーララ州のマラヤーラム語映画ソング「Entammede Jimikki Kammal」
「Bollywood」に対して、マラヤーラム語映画は「Mollywood」と呼ばれるらしい。
(歌詞)
着替えて
Ini vesham mareda「Malayaattoor教会」へ行って
malayattoor church十字を切ろう
Kurishum koda neram
使徒トマスはケーララに上陸後、地元の人の迫害にあい、丘の上に逃れ、岩に十字架を描いて祈ったところ、神の加護を得てタミル・ナードゥまで布教を続けることができたという。
さらに、その岩から血が出たり、岩の十字架が黄金に輝いたりという伝説もあるそうです。
その丘は「Kurishumudi」(Hill of the holy cross/聖十字の丘)と名付けられ、「Malayaattoor教会」が建てられ、インドのキリスト教徒の大切な巡礼地になっているようです。
ちなみに2011年の国税調査によると、インドのキリスト教徒は約2800万人。
人数ではケーララ州とタミル・ナードゥ州が多い。
| 州 | 人口 | 割合 (%) | 人数 |
|---|---|---|---|
| インド全土 | 1,210,854,977 | 2.30 | 27,819,588 |
| ケーララ州 | 33,406,061 | 18.38 | 6,141,269 |
| タミル・ナードゥ州 | 72,147,030 | 6.12 | 4,418,331 |
使徒トマスは、「イエスが復活した」という他の弟子たちの言葉を信じず、自分で確認したという話から「疑い深いトマス」と呼ばれるようになったそうです。
歌詞のサビは、意味深?
お母さんのイアリングは
Entammede jimikki kammal
お父さんに盗まれ
Entappan kattondu poye
お父さんのブランデーは
Entappante brandy kuppi
お母さんに飲み干された
Entamma kudichu theerthe
(参考)
Thesaurus:Hindi/God - Wiktionary.
Rabb - Wikipedia
ख़ुदा (xudā)/रब (rab) - Wiktionary
Khuda - Wikipedia
Why do Sikh people keep calling Rab which is Islamic Word and ...
Malayatoor Church - Wikipedia
Thomas the Apostle(Mission in India) - Wikipedia
Christianity in India(St. Thomas) - Wikipedia
Entammede Jimikki Kammal
| 歌手 | Vineeth Sreenivasan, Renjith Unni |
| 映画 | Velipadinte Pusthakam |
| 公開 | 2017年8月16日(映画) |
| 歌詞翻訳サイト | LyricsTranslate |
Tu Jo Mila
| 歌手 | K.K. |
| 映画 | Bajrangi Bhaijaan (Wikipedia) |
| 公開 | 2015年 |
映像
歌詞
日本紀元(Nihon Kigen) 東洋をつくった景教⑩達磨と使徒トマス
インドから中国に禅の仏教を伝えた人とされています。 しかしこのだるまに関し、京都の金戒光明寺に、 興味深い絵が保存されています。 景教研究家のエリザベス・A・ゴードン女子が、 住職の許可を得て撮影した仏教画ですが、 もとは中国から伝来したといいます。 法然上人によって発見されたとの伝説があり、 従って12世紀以前に描かれたものでしょう。 絵は、上中下の3段から成り、 下段では達磨(頭に布をかぶっている人物)が、 人々に語っている光景となっています。 中断では、一同が空虚な墓の前に行っています。 そして上段では、
























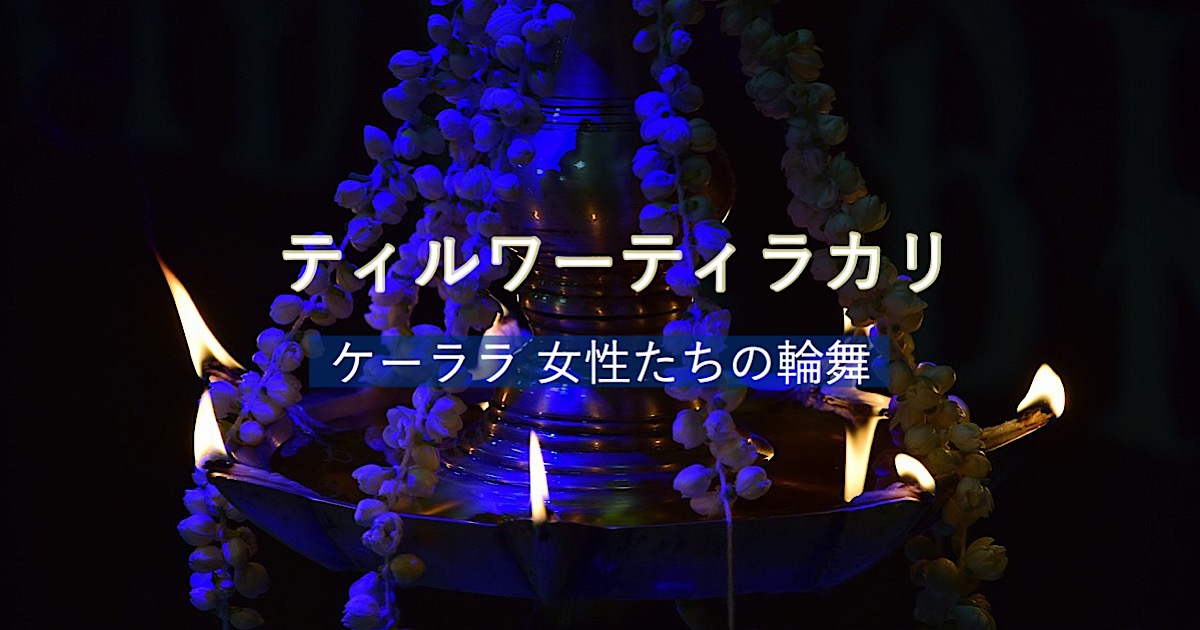

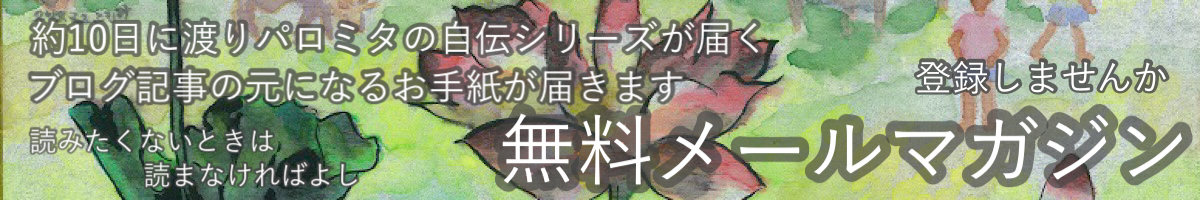



0 件のコメント:
コメントを投稿